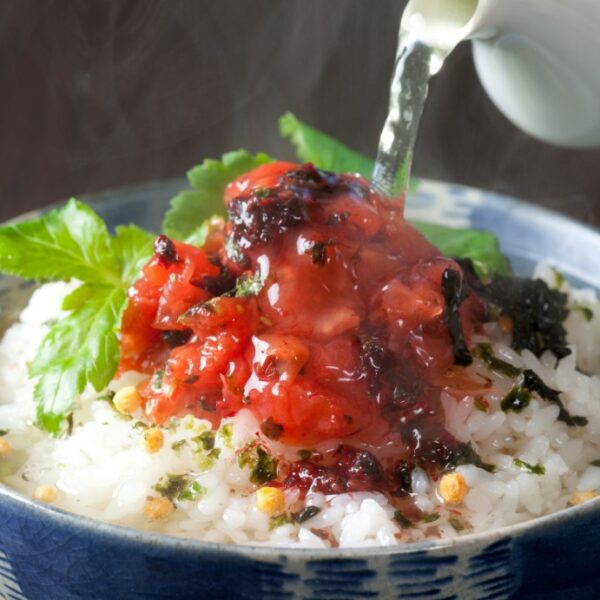今更だけど「梅酒」のおいしい飲み方、知ってる? 梅酒の度数とおすすめの割り方、料理への活用術とは
「梅酒の度数ってどれくらいなんだろう」
「梅酒をおいしく飲むにはどうしたらいいのか」
この記事にたどり着いたあなたはそんな疑問を感じたことがあるのではないでしょうか。
スーパーや酒屋でも豊富な種類が入手できて、甘味と酸味が絶妙なバランスで飲みやすいことから、老若男女に人気な梅酒ですが、実はビールよりも度数が高いため、ストレートやロックの他にもさまざまな飲み方があります。
この記事では、梅酒の情報や飲み方、料理への活用術について解説していきます。
たくさんありすぎて一度にはご紹介しきれないため今回は一部の代表的な例に留めますが、まずは梅酒を楽しんでみよう!と思っている方はぜひチェックしてみてくださいね!

Contents
梅酒のアルコール度数は平均で15度前後
梅酒のアルコール度数は一般的に15度前後が多いといわれています。
アルコール度数15度前後というとワインや日本酒と同程度で、ビールが5度前後であることを考えると、梅酒はアルコール度数がやや高めのお酒であることがわかります。
その口当たりの良さから、ワインや日本酒よりも飲みやすいという感想を多く耳にしますが、ビールや清涼飲料のように飲むと、思った以上のアルコールを摂取することとなるため注意が必要です。
また、梅酒は、酒税法によりリキュールに分類されるお酒となります。リキュールとは、蒸留酒に香味をつけて、砂糖やシロップなどを加えて仕上げたお酒の種類で、カクテルにして飲まれることが多いものです。リキュールのアルコール度数は5〜64度程度と幅広いですが、その多くは20度程度ですので、梅酒はリキュールの中ではアルコール度数がやや低く飲みやすいお酒といえるでしょう。
梅酒は市販品と自家製でアルコール度数が大きく異なる場合があるので、楽しく飲めるように以下のポイントに分けて紹介します。
・市販の梅酒のアルコール度数は8~15度
・自家製の梅酒のアルコール度数は30度を超えることも
市販の梅酒のアルコール度数は8~15度
スーパーや酒屋などで買える梅酒のアルコール度数は8〜15度程度です。
ブランドによっても異なりますが、市販の梅酒はアルコール度数を下げて飲みやすくしています。
自家製の梅酒のアルコール度数は30度を超えることも
自家製の梅酒の場合、アルコール度数は市販のものと比べて高く、30度を超えることもあります。
自家製の梅酒には、腐敗を抑えるためにアルコール度数が35度程度のホワイトリカーという蒸留酒が使用されています。ホワイトリカーに梅を漬けてエキスを抽出していくため、梅酒が仕上がった時にはアルコール度数が20〜30度となります。
ちなみに、アルコール度数が20度未満のお酒で梅を漬けることは酒税法で禁止されています。アルコール度数が20度未満のお酒を使用すると、再発酵により新たなアルコールが発生する可能性があるためで、安全にお酒を飲むためにも一つのボーダーラインになっているのです。
おいしくて飲みやすい!度数控えめな梅酒の割り方
そのまま飲むとアルコール度数が高めの梅酒ですが、他のソフトドリンクと割ることで飲みやすいアルコール度数まで下げて飲むことができます。
ここからは、梅酒をおいしく飲むための割り方を紹介していきます。
水・お湯・ソーダ
まずはシンプルに梅酒を薄める水割り、お湯割り、ソーダ割りです。
水割りは、アルコールには強くないけど梅酒の味をそのまま味わいたいという方におすすめです。
お湯割りは梅の香りを強く感じられる飲み方です。身体を温めてくれるので寒い時期にもピッタリ!
ソーダ割りは梅酒の甘味を抑えつつ、梅のほのかな香りに炭酸の爽やかさをプラスした飲み方です。ライムやミント、レモンをほんの少し加えることで爽快感が強くなり、揚げ物などの食事に合うお酒になります。
【割合】
・水割り(梅酒1:水1 氷適量)
・お湯割り(梅酒1:70度くらいのお湯1)
・ソーダ割(梅酒1:炭酸水1 氷適量)
オレンジジュース
次に紹介するのはオレンジジュースで割る飲み方です。
一見甘い飲み物同士に見えますが、オレンジジュースの酸味が梅酒の甘酸っぱさと合わさってカクテルのような味わいになります。この場合、甘さ控えめでさっぱり系の梅酒と合わせるのがおすすめで、お酒が苦手な方でも飲みやすい味わいと風味に仕上がります。さらに、炭酸水を入れることで爽快感が加わるのでこちらもおすすめです。
【割合】
オレンジジュース割(梅酒1:オレンジジュース1~2 氷適量)
オレンジジュースと炭酸割(梅酒1:オレンジジュース1~2:炭酸水1 氷適量)
緑茶・紅茶
続いて、緑茶や紅茶などのお茶割りで飲む方法を紹介します。
甘さを抑えてくれるお茶で梅酒を割ると、さっぱりとした味わいになります。甘いお酒が苦手な方や食事と一緒に飲みたい方におすすめです。緑茶や紅茶のほかにも、ウーロン茶やジャスミン茶などお茶の種類で味わいが大きく変化するほか、ペットボトルではなく茶葉から入れたお茶を使うと、香りが良く本格的な味わいになるなど、奥深い味わいを楽しむ飲み方ができます。
【割合】
お茶割り(梅酒1:お茶5)
牛乳・飲むヨーグルト
最後に、梅酒を牛乳や飲むヨーグルトで割る飲み方を紹介します。
少し珍しい組み合わせですが、牛乳や飲むヨーグルトで割ると、梅酒の酸っぱさが抑えられるため、口当たりが柔らかでまろやかな味わいになります。黒糖梅酒のようなとろみがある濃厚なものも含め、実は、どんな梅酒にも合わせやすい飲み方です。注意点は、梅酒を牛乳で割ると分離したり固まったりすることがあることです。牛乳には、温めた際に表面にできる膜でお馴染みのカゼインというタンパク質が含まれているのですが、カゼインは酸性の液体と混ざると固まるという性質を持っています。梅酒は酸性の液体にあたるため、牛乳を混ぜると成分的に変化が起きてしまうことがあるのです。もちろん、そのまま飲んでも害はありませんが、梅酒と牛乳を氷などでよく冷やしてから混ぜ合わせると成分変化が起きにくくなるため、気になる方はこうした点に気を付けて作ってみると良いでしょう。
【割合】
牛乳・飲むヨーグルト割(梅酒1:牛乳・飲むヨーグルト2 氷適量)

アルコール度数高め!上級者向けの割り方
ここからは、アルコール度数が高めのまま飲む割り方を以下の4つに分けて紹介します。アルコールに強い方はぜひ試してみてくださいね。
・ロック
・ウイスキー
・ワイン
・焼酎
ロック
1つ目はロックで、梅酒に氷だけを入れて飲む飲み方です。
氷が溶けていくことで薄まっていきますが、アルコール度数は大きく下がらないので、梅酒本来の味わいをダイレクトに楽しめる飲み方です。グラスをあらかじめ冷やしておくことで、氷が溶けるのを遅らせることができるため、薄まらずに濃厚な梅酒の味わいを楽しむことができます。
ウイスキー
2つ目はウイスキーと割る飲み方です。
梅酒にウイスキーを混ぜるカクテルで、梅酒の甘酸っぱい味わいがウイスキー独特のクセを抑えてくれるため、飲みやすくなる相性の良い組み合わせです。ウイスキーと割る場合は、梅酒よりもウイスキーの方がメインのお酒となり、香り豊かな味わいとなります。また、炭酸水を入れることでより爽やかな味わいを楽しめる梅酒ハイボールにすることもできます。梅酒にも多くの種類がありますが、ウイスキーも多種多様なブランドがあるため、ウイスキーと混ぜることでさまざまな味わいを楽しむことができます。
【割合】
ウイスキー割(梅酒1:ウイスキー3)
梅酒ハイボール(梅酒1:ウイスキー3:炭酸水10~12)
ワイン
3つ目はワイン割りです。
意外かもしれませんが、梅ワインという梅を使って作るワインもあり、相性がいい組み合わせなのです。赤・白・ロゼのどのワインで割っても楽しめますが、特に白ワインだとすっきりとした味わいが梅酒の甘さを抑えて、より上品なお酒に変化します。スパークリングワインを使うとよりさっぱりとおしゃれな味わいとなるので、こちらもぜひ試してみてください。
【割合】
ワイン割(梅酒1:ワイン1)
焼酎
4つ目は焼酎割りです。
アルコール度数を薄めるのではなく、アルコール度数を高めて飲む割り方で、焼酎の独特な香りを梅酒のフルーティーな香りが和らげるため、アルコールの匂いが苦手な方でも飲みやすくなります。おすすめは、アルコール度数が高くない梅酒と香りにクセがない甲類焼酎を使うこと。焼酎割りの梅酒は飲みやすいですが、ロックやストレートで飲む場合よりもアルコール度数が高くなるため、飲みすぎには注意しましょう。
【割合】
焼酎割り(梅酒1:焼酎1)
梅酒を料理やデザートに活用する方法
ここまで梅酒のさまざまな飲み方を紹介しましたが、梅酒は飲み物として飲むだけではなく、料理やデザートに活用する方法もあります。ここからは梅酒を使った料理やデザートを紹介していきます。
料理
チキンソテー
梅酒は鶏肉や豚肉に合う調味料として活躍させることができます。
ここでは梅酒をチキンソテーに活用する方法を紹介していきます。
【材料(4人分)】
・鶏もも肉 2枚
・塩こしょう 適量
・小麦粉 適量
・サラダ油 大さじ1/2
・梅酒 大さじ4
・醤油 小さじ1/2
【手順】
1.鶏肉の筋を切るように切り込みを入れて両面に塩こしょうをつける
2.10分ほどおいたら小麦粉をまぶす
3.フライパンでサラダ油を加熱し、鶏肉を皮目が下になるようにフライパンに入れ、蓋をして4分ほど中火で焼く
4.裏返して2分ほど中火で焼いたら、弱火にして3~4分蒸し焼きにする
5.火を止めずに梅酒を加えて、煮立ってきたら醤油を加えて絡める
6.鶏肉を取り出して食べやすいサイズに切ったら、盛り付けて完成!
完成したら、野菜炒めと合わせて焼き汁をかけると、よりおいしく食べることができます。鶏もも肉の脂が梅酒と組み合わさることで爽やかな味わいに変化するため、脂が多く量が食べられないという方のお箸も進むはず!
デザート
ここからは梅酒で作るデザートを紹介していきます。
ゼリー
梅酒で簡単に作れるデザートとして、梅酒ゼリーを紹介していきます。
梅酒ゼリーの作り方は基本的に以下の通りです。
【材料(4カップ分)】
・梅酒 100cc
・水 300ccと大さじ2
・ゼラチン 5g
・砂糖 大さじ5
【手順】
1.水大さじ2とゼラチンを混ぜてふやかす
2.水300ccと梅酒、砂糖を鍋に入れて加熱し、沸騰する直前に火を止める
3.1で作ったゼラチンを2と混ぜて溶かす
4.粗熱が取れたらお好みのカップに入れて冷蔵庫で冷やす
5.しっかりと固まったら完成!
梅酒ゼリーはフルーツゼリーよりも爽やかな甘味を感じられるデザートですが、市販ではなかなか売っていないので、自宅で作るのにおすすめです。梅酒ゼリーを作る際に加熱する工程がありますが、お子様と楽しみたいときには沸騰させてアルコール分をよく飛ばしましょう。砂糖やはちみつを多めに入れるとお子様でも食べやすいゼリーになるので、お好みに合わせて作ってみてくださいね。
アイス
梅酒はアイスとの相性も抜群です。近年SNS上でも話題になっている組み合わせで、バニラアイスに梅酒を垂らすだけで出来上がり!バニラアイスの甘味に梅酒のさっぱりとした酸味が程良く合わさり、絶品スイーツに変身します。特に、コクと深い味わいを感じられる黒糖梅酒やフルーティーなにごり梅酒の組み合わせがベストマッチ。バニラアイスの他にも、ジェラートやスムージーにしてもおいしく楽しめるのでぜひお試しくださいね。
梅樹園オリジナル梅酒がおすすめ!
お酒というジャンルの中では決してアルコール度数は低くない梅酒ですが、飲み方によってアルコール度数を調整でき、割り物によってさまざまな味わいを楽しむことができます。また、料理やデザートとしても楽しめる、まさにオールラウンダーなお酒です。
さらに、梅酒には、健康や美容に嬉しいさまざまな効果・効能があるので気になる方はこちらの記事も読んでみてください。
「おいしい梅酒を飲んでみたい」「こだわりの梅酒をプレゼントしたい」という方は、プラムレディの“梅樹園オリジナル梅酒「B」”がおすすめです。こちらは紀州南高梅の完熟梅と青梅を贅沢に使用した二段仕込み製法で作られた梅酒で、完熟梅の芳醇な香りと甘みに加えて、青梅の酸味も加わり、すっきりと爽やかな味わいを楽しむことができます。
皆さんも飲みすぎに気をつけながら、梅酒ライフを楽しんでくださいね。