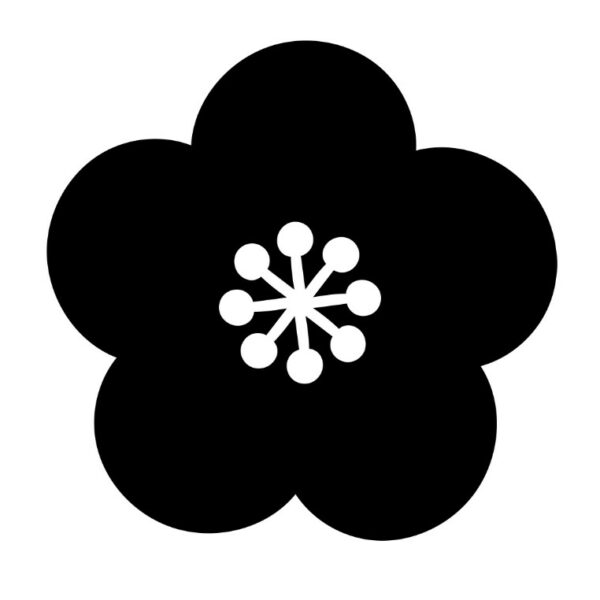干すのが面倒?そんな人には手軽でおいしい梅漬けがおすすめ!
梅干しづくり、憧れるけれど「干す時間がない」「広げる場所がない」と尻込みしてしまうあなたへ。じつは、干さなくても作れる“梅漬け”があるんです。作り方はとってもシンプル、洗って塩に漬けるだけ。まるでインスタントラーメン並みの手軽さなのに、味は本格派。しっかり酸っぱくて、塩気もキリッと効いて、ご飯のお供にぴったりです。
今回はそんな手軽さが魅力の「梅漬け」の作り方から、保存のコツ、アレンジ方法まで、初心者さんでも楽しめる“干さない梅生活”の始め方をご紹介します!
干す工程を省くだけで、梅しごとのハードルはぐっと下がります。「気になってはいたけど…」という初心者さんにもぴったり。さあ、一緒に梅ライフの扉を開きましょう!

Contents
「梅漬け」と「梅干し」ってどう違う?
「梅干し」と「梅漬け」、名前は似ていても実は別モノ。スーパーの棚でも見かけるけれど、違いがいまいちピンとこない…そんな方も多いのでは?本章では、表示基準や見た目、香りと味の観点から、この“梅の双子”の違いを、わかりやすくご紹介します。知れば納得、味わえばもっとハマる、梅の世界へようこそ!
市販の梅製品の表示基準
実は、梅干しと梅漬けの違いは、食品表示基準にもバッチリ明記されています。農林水産省によると“「梅干し」は「天日干しを含む干し工程があるもの」”に限ってそう名乗れるのです。干していないものは「梅漬け」と表示されるのがルール。つまり、「干しているかどうか」が梅製品の名前を分ける最大のポイント。とはいえ最近では、「梅干し風梅漬け」など、表示と実態にややギャップのある商品もちらほら。ラベルを見るだけでなく、製法にも目を向けると梅リテラシーがグンと上がりますよ!
梅干しと梅漬けの見た目の違い
見た目にも、干すか干さないかの違いが現れます。梅干しは表面がシワシワでやや硬め、梅漬けはふっくらツヤツヤ。干すことで水分が抜け、実が締まるため、梅干しは「年季の入った旅人」のような風格に。一方、梅漬けは「つけたての若者」、みずみずしく柔らかな印象。お弁当に入れるときのビジュアルにも差が出るので、お好みで使い分けると◎。ちなみに、どちらも赤く色づいていれば、それは紫蘇の力。色がない「白干し」や「白漬け」も、素材感が引き立って美しいですよ。
香りと味の違い
香りと味でも、梅干しと梅漬けはしっかり個性派。梅干しは酸味がガツン!と強く、時を経た深みのある香りが特徴。一方、梅漬けはフレッシュな香りと塩味が印象的。漬けたてならではのジューシーさがあり、果物感を残した味わいが魅力です。梅干しは長期保存に適し、食卓の常備菜的存在。梅漬けは、季節の味として食べる、旬のごちそう。どちらも甲乙つけがたし、ですね。シーンや好みに合わせて選ぶのが、梅ツウのたしなみです♪

干さない「梅漬け」の作り方
「梅干しは手間がかかって難しそう…」そんなイメージをくつがえすのが、干さずに漬ける「梅漬け」です。実は、塩と梅があれば、あとはほぼ放っておくだけ!作り方もとってもシンプルで、初心者でも失敗知らず。しかも、ジップロックで作れるお手軽さ。今回は、材料選びのポイントから、成功のコツまでを“豆知識”付きで一挙公開。おうちで梅仕事、始めてみませんか?
材料と準備
● 材料(梅1kg分の目安)
- 完熟梅:1kg(黄熟し、香りがしっかりあるものがベスト)
- 粗塩:180g〜200g(梅の重さの18〜20%)
- 焼酎:適量(35度前後・消毒用として使用)
- ジップロック(Lサイズ):1〜2枚
- 重し用の袋(水を入れたジップロックなどでも可)
- バットやタッパー(ジップロックを安定させるため)
【豆知識:塩の量、どうする?】
塩が少ないとカビやすくなるので注意。長期保存したいなら20%がおすすめだけど、すぐ食べたいなら18%でもOK。塩分を下げすぎると“梅ジャム未遂事件”になりかねません!
【豆知識:焼酎の役割】
焼酎はアルコール度数が高いため、梅の表面についた雑菌をやっつけてくれる頼れる消毒係。仕込み前に梅をサッとくぐらせるだけで、失敗率がぐっと下がるよ!
作り方の手順
1.梅を洗う
まずは梅を水でやさしく洗い、表面のホコリや汚れを落とします。こすらず、やさしく手でなでるように。完熟梅はデリケートだから、ここは「触れるというより、寄り添う気持ち」
【豆知識 :梅の完熟具合】
黄色く色づき、甘い香りがしていたら「今がチャンス!」という合図。青梅は硬く、渋みが残ることがあるので、完熟梅での仕込みが鉄則です。
2.ヘタを取る
竹串や楊枝で、梅のおへそのような部分(ヘタ)をやさしく取り除きましょう。残っていると、そこからカビが生えやすくなるので、地味だけど大事な工程!
3.水気をふき取り、焼酎をまぶす
洗った梅はキッチンペーパーなどでしっかり水気をふき取り、消毒用の焼酎を全体にまぶします。手でコロコロ転がしながら全体に行き渡らせてくださいね。
【豆知識:なぜ焼酎?】
焼酎のアルコールは、梅の表面にいるカビの原因菌を抑えてくれるお助けヒーロー。飲んでよし、梅にかけてよし。まさに万能選手!
4.塩とともにジップロックに入れる
塩の半量をジップロックの底にまき、その上に梅を並べます。そして残りの塩を全体にまぶすように振りかけていきます。
【豆知識:塩はまんべんなく!】
塩が梅の表面に均等についていないと、味ムラが出たり、カビが発生しやすくなります。「梅はみんな平等に扱ってあげる」が成功の秘訣♪
5. 重しをする
ジップロックの空気をしっかり抜いて密閉し、バットやタッパーに寝かせます。さらにその上に、水を入れた別のジップロックなどで重しをして、冷暗所で保存します。
【豆知識:重しって必要?】
重しがないと梅酢が上がりにくくなります。梅酢は天然の保存液。梅がしっかり梅酢に浸ることで、保存性も風味も格段にアップ!
6.梅酢が上がったら
1週間ほどで梅酢が梅を覆うくらいに上がってきます。ここまで来れば成功は目前!梅が完全に漬かっていれば、そのまま冷蔵庫で保存もOKです。
【豆知識:梅酢の活用法】
捨てるなんてもったいない!梅酢は、ドレッシングや浅漬け、炊き込みご飯にも使える万能調味料。まさに“梅から生まれた魔法のしずく”。
おいしい「梅漬け」を作るコツ
手順を守ろう
梅漬け作りの最大の敵は“油断”です。材料も手順もシンプルだからこそ、基本の流れを丁寧に守ることが成功のカギ。たとえば、梅のヘタ取りをうっかりスキップしたり、水気がしっかり取れていなかったりすると、カビの温床に…。特に完熟梅はとてもデリケートなので、優しく扱ってあげましょう。「簡単=雑でOK」じゃない!愛情をもって梅と向き合えば、ちゃんと応えてくれるんです。梅仕事は“心の余裕”も育ててくれる、実はすごい家事だったりして。
梅の格言:急がば回れ、梅仕事は手間の中にコツがある!
塩分濃度に注意!
梅漬け初心者がやりがちなのが、「健康のために塩を少なめにしようかな?」という罠。実はこれ、保存食としての梅にとってはNG。塩は防腐剤として働いてくれる大事な存在で、18〜20%はしっかり確保したいところ。これより低いと、カビや発酵で失敗するリスクが一気に上がるんです。逆に、ちょっと塩が多くても、食べる前に塩抜きすれば味の調整は可能。だから、最初は「攻めより守り」がおすすめ!
梅の格言:塩は保存の味方!江戸時代の梅干しは30%塩分が当たり前。

梅漬けを作るなら「紀州南高梅」がおすすめ
梅漬けの魅力は、手軽さと素朴なおいしさ。だけど、梅の質で味がグンと変わるのも事実。そこでぜひおすすめしたいのが、日本一の梅ブランド「紀州南高梅」。果肉が厚くてやわらかく、皮は驚くほど薄い――つまり、漬けたあともふっくらジューシーな仕上がりになるんです。まるで梅の女王。特に初心者でも扱いやすく、失敗しづらいのも高ポイント!せっかく手作りするなら、素材にもこだわって、自分史上最高の梅漬けを目指してみませんか?お買い求めはこちらから。